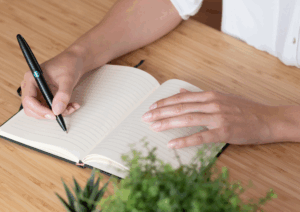「できなくなった」に囚われない――研修後の定着支援で大切な視点とは?
研修後の定着支援で「実行状況を報告してください」とアクションプランの実施回数を確認すると、
ほとんどの受講生が1週目は「よくできた」「できた」と元気よく答えてくれます。
しかし、2週目になるとその割合はぐっと減り、3週目、4週目…と時間が経つほど
実施回数も減っていく――これは現場で珍しくない傾向です。
この現象は実はとても自然なことです。
研修が終わったばかりの時に感じる高揚感やワクワク感――その感覚があるうちは誰もが「よし、やるぞ!」と前向きになります。
ですが日々の忙しさや業務に追われていれば、モチベーションや実践頻度が下がるのはある意味当然です。
人生観が変わるような映画を観たとき、その直後には「自分も変わろう」と思っていたのに、気づけばいつもの自分に戻っていた(苦笑)――このような経験をされたことがある方も多いと思いますが、修後の行動計画もまさにそれと同じなのです。
それは、人が「変わる意欲」も「元に戻る力」も同時に持っている生き物だからです。
だからこそ、定着支援で重要なのは「1週目より回数が減った」にこだわりすぎないことです。
むしろ、研修前は「実行回数がゼロ回」だったのに、今は何回かでも実践できているというのは、十分に前進なのです。
大切なのは、「今週は1週目よりペースが落ちたな」と落ち込むのではなく、「そもそも研修前に比べて、ちゃんと新しい行動ができているか」「どこが続けやすかったか」と、変化のベースラインにしっかり目を向けること。
加えて、高揚感の中で突き進んだ1週目の数字を「これが本来の目標だ」と勝手にずらさないことも要注意です。
初期の勢いに流されず、「日常の中で無理なく続けられるペースはどれくらいか」「現実的に続けるには何が必要か」と、落ち着いた視点で次の目標設定をすることが、定着支援の肝になります。
減ったこと=ダメ、ではありません。
続けていること=大きな変化。
「研修前との違い」と、「自分で無理なく続けられるペース」に目を向けることで、研修の学びはしっかり日常に根づいていきます。
定着支援は、一人ひとりに寄り添い、前進を見つける応援でもあるのです。
ぜひ、「できなくなっている」という指標にとらわれることなく、継続による自分自身の成長を楽しんでみてください。